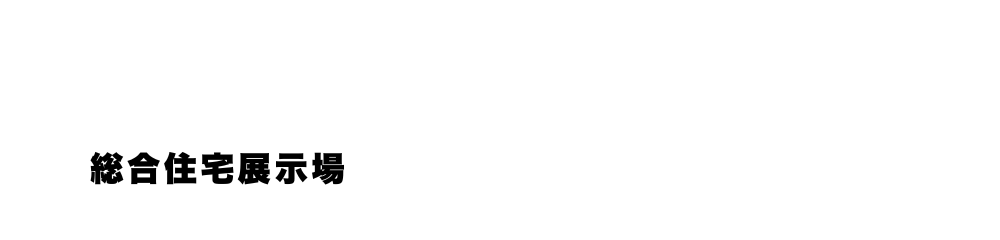「収納が多い=快適」は思い込み?後悔しない収納計画のカギは“配置と導線”#column
この記事では以下のような疑問に答えます:
- なぜ「収納は多い方が安心」という考えが落とし穴になるのか?
- 実際の生活で明らかになった、収納配置の失敗例
- スムーズな生活動線と収納の関係とは?
- モデルハウスでしか気づけない“使える収納”のチェックポイント
最初に伝えたいこと
注文住宅の打ち合わせで「収納は多ければ多いほど安心」と感じるのは、ごく自然なこと。でもその安心感が、住んでから「なんか暮らしにくい…」という後悔につながることがあるんです。
本当に快適な住まいには、ただ量がある収納ではなく、“動線と使いやすさ”に配慮した収納が必要不可欠。この記事では、実際に起きた“収納の落とし穴”をもとに、後悔しない収納計画のポイントをお届けします。
【1】収納だらけの家が「住みにくい家」になった理由
千葉県在住の鈴木さん夫妻は、2人の子どもと暮らす理想のマイホームを建築。しかし完成してみると、収納の“多さ”が裏目に出てしまいました。
たとえば…
- 玄関の大きな土間収納
- キッチン背面のフルサイズパントリー
- リビングの大容量ファミリークローゼット
- 子ども部屋にそれぞれ備えた壁一面の収納棚
住む前は「完璧な収納計画」だったはずが、暮らしてみると…
「使ってない収納、多すぎるかも…」
【2】収納が生活の“邪魔”になることもある
最大の誤算はリビングの収納でした。
キッチンから洗面所へと向かう通路上に、収納スペースが張り出すかたちで設けられており、通路幅がわずか90cmほどに。子どもたちがすれ違えず、洗濯物を抱えて通るのも一苦労。
しかもその収納の中身といえば、季節外れの飾り物や処分しそびれた書類など、ほぼ“開かずの間”。
「この収納、本当に必要だったのかな…」
と奥さまは苦笑い。
【3】“安心感”で作った収納がストレスに変わる
収納を増やしたい理由の多くは、「物が多いから仕舞いたい」「将来困らないように」という不安から。でも、収納スペースが多ければ多いほど「捨てられない物」が増えて、結局は家の中が片付かなくなるという皮肉な結果も…。
収納は**“多さ”より“場所とサイズ”**が重要です。
たとえば:
- 玄関:靴・ベビーカーだけなら1畳でOK
- リビング:日用品程度で十分。大型収納は不要
- キッチン:大きすぎるパントリーは動線の妨げに
目的が曖昧な収納は、ただの“空間の浪費”になりかねません。

【4】図面だけじゃ分からない“収納の罠”は、展示場で発見できる
平面図や3Dパースでは、収納の「使い勝手」や「圧迫感」までは想像しづらいのが現実。
だからこそ、モデルハウスを実際に歩いて体感することがとても大切です。
こんな発見があります:
- 「ここに収納あるのに、動線上まったく目に入らない」
- 「掃除機をさっとしまえる場所、意外と便利!」
- 「この奥行き…逆に物を取り出しづらいな」
最低でも3〜5軒のモデルハウスを見比べてみると、自分にとって本当に使いやすい収納の形が見えてきます。
【5】後悔しない収納計画のための3つのポイント
注文住宅で収納に失敗しないために、ぜひ覚えておきたいのがこの3つ:
1. 「なんとなく収納」はやめる
→ 何を入れるのか、使い道を具体的にイメージしておくこと。
2. 家事動線に収納をかぶせない
→ 通路の妨げになるような配置は避け、動線優先で考える。
3. 実物で“使いやすさ”を検証する
→ 展示場で実際に開け閉めして確認。図面より体験!
終わりに:収納は“動き”とともに生きる
収納は確かに大事。でも、「あればあるほどいい」という考えは、実際の生活にそぐわないこともあります。大切なのは、暮らしの中で自然に使える配置と、無理のないサイズ感。
もし今、収納計画に迷っているなら、ぜひ展示場に足を運んでみてください。歩いて、見て、触れて、自分自身の生活にフィットする収納を見極めてくださいね。