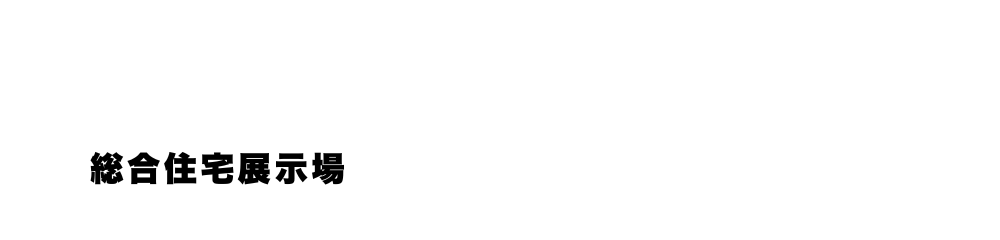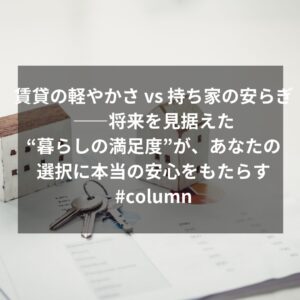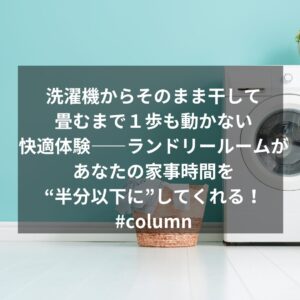子ども部屋は狭くても大丈夫!整理収納で広さ以上の快適空間をつくる方法#column
この記事を読めば分かること
- 子ども部屋の広さはどのくらいが理想か
- リビング学習と子ども部屋のバランスの考え方
- 「1人で寝るタイミング」をどう決めればよいか
- 自立心を育てる子ども部屋と収納の工夫
- 独立後に子ども部屋をどう活用するか
はじめに
家を建てるときに、多くの人が迷うテーマのひとつが「子ども部屋をどうするか?」です。広さは? 必要なタイミングは? 狭くても大丈夫? そして将来、子どもが独立した後はどう使えばいいのか。
この記事では、中学2年生と小学5年生の母であり整理収納アドバイザーとして数多くの家庭を見てきた経験をもとに、あなたが子ども部屋のことで迷わなくなる具体的な考え方と工夫をお伝えします。
狭くても大丈夫?子ども部屋の広さのリアル
「子ども部屋は最低5〜6畳が必要」とよく言われますが、実際は4.5畳でも十分可能です。ただし、部屋の形が細長かったり凸凹していたりすると、ベッドと机を置くだけで精一杯になってしまうことも。
そこで重要になるのが 整理収納の力 です。収納がうまく作られていれば、狭い部屋でもスッキリ快適に使えます。
たとえば我が家のケース。長男の部屋は約5.3畳、長女は約5.5畳と決して広くはありませんが、ベッド・机・本棚を配置しても窮屈に感じません。理由は、物を必要以上に持たず、収納場所を明確にしているからです。
リビング学習だけで本当に足りるのか?
最近人気の「リビング学習」。親の目が届きやすく、小学校低学年までは特に効果的です。
しかし、小学校中学年以降になると持ち物が急増し、友達との交流や一人時間のニーズも高まります。その時に「やっぱり自分の部屋が欲しい」となるケースが多いのです。
つまり、リビング学習をしながらも 子ども専用のスペースを用意しておくことが将来の安心につながる のです。収納も同じで、親が全部管理するのではなく「子どもが自分で出し入れできる場所」を設けることが、自立心を育てる第一歩になります。
1人で寝るタイミングに正解はない
「子どもはいつから自分の部屋で寝るのが良いの?」と悩む親は多いでしょう。
日本では川の字で寝る文化が根強く、一緒に寝ることが当たり前。でも海外ではベビー期から一人寝が基本という家庭も少なくありません。
正解はありませんが、気をつけたいのは タイミングを逃さないこと。せっかく用意した子ども部屋が物置状態になり、ベッドを入れるのが面倒になってしまうケースもよくあります。
我が家では長男が小1の時にベッドを置きましたが、完全に一人寝を始めたのは小2の頃。まだ妹と布団を並べて寝たこともあり、それも今となっては良い思い出です。

自立を育てる「物との付き合い方」
子ども部屋は単なる寝る場所ではなく、自立心を育てるトレーニングの場 でもあります。
整理収納アドバイザーとして意識しているのは「物を与えすぎないこと」。持ち物が多ければ多いほど管理が大変になり、片付けも習慣づきません。
また、家事に参加させることも自立の一歩。洗濯物を畳んで自分の服を片付ける、使った食器を自分で下げる…。一見手間に思えても、こうした小さな積み重ねが「自分のことは自分でできる」力につながります。
最近では中1の息子が料理を手伝ってくれるようになり、成長を感じられる瞬間が増えてきました。
子どもが独立した後、部屋はどうする?
子ども部屋は、子どもが巣立った後も有効に活用したいものです。
例えば「趣味部屋」「在宅ワーク用の書斎」「帰省時の宿泊部屋」として使うのもおすすめ。
ただし注意したいのは、子どもの物をそのまま残しっぱなしにしてしまうこと。
「勝手に触れないから…」と放置していると、あっという間に10年以上経ってスペースが無駄に。節目のタイミングで片付けて、新しい役割を与えることが大切です。
まとめ
子ども部屋に正解はありません。
大切なのは、広さよりも「整理収納」と「成長に合わせた柔軟な使い方」。
リビング学習と専用スペースの両立、1人寝のタイミング、持ち物の管理、自立心を育てる工夫…。これらを意識するだけで、子ども部屋は狭くても十分に機能します。そして、子どもが独立した後も部屋を有効活用することで、暮らしの質はぐっと上がります。
あなたの家づくりや子育ての参考にしていただければ幸いです。